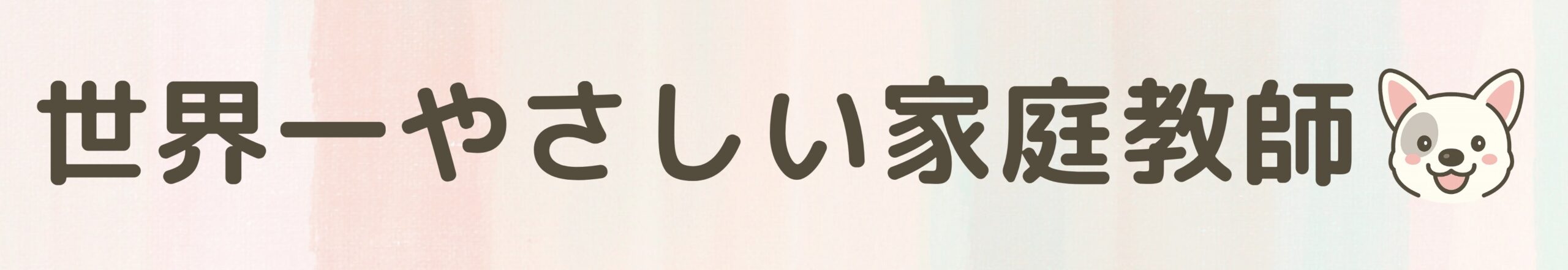こんにちは、”世界一やさしい英語講師“として活動中のRikaです♪
この記事では、聞き流すだけでリスニングが上達したり、英語が話せるようになるのか、という点について考察致します。

へ~!とりあえず英語の音楽とか音声を聞き流すだけでも耳が慣れたり多少効果あると思ってたな~。

もちろん耳を慣らしたいとか、英語自体への抵抗を減らず方法として有効な場合もありますが、英語が聞き取れて理解できるようになるトレーニングとしては、残念ながら聞き流すだけだと不十分ですね。

そうなのか~。おいらは勉強があまり得意な方じゃないから、あまり労力をかけずに楽しく英語を身につけたいな~。

多くの方々が同じように思っていますよね♪なぜ聞き流しがダメなのかという理由について今回は簡単に説明しますね!
「聞き流し英語」のよくある誤解

英語学習はマラソンのような精神力・体力勝負の長期戦です。
本当に地道な作業を積み重ねる毎日なので、たまに上手くいかなくてもどかしくなったり、楽な方に逃げたくなったりしますよね。
そういった時に、以下のような考えに至ったことありませんか?
- 耳を英語に慣らすために家事や通勤の合間にとりあえず英語の音声流しておこう!
- とりあえず洋画を字幕無しで観てみよう!
- 聴くだけで英語が上達する教材があるらしい!買ってみよう!
- 洋楽の曲を流して英語耳になろう!
お気持ちはとってもよく分かるのですが、残念ながらこれだけでリスニング力が飛躍的に伸びたり、聞いた英文を会話の中でスラスラ使えるようになることはないです。
聞き流すだけでは上達しない理由
①聞こえる音の意味が結局分からない
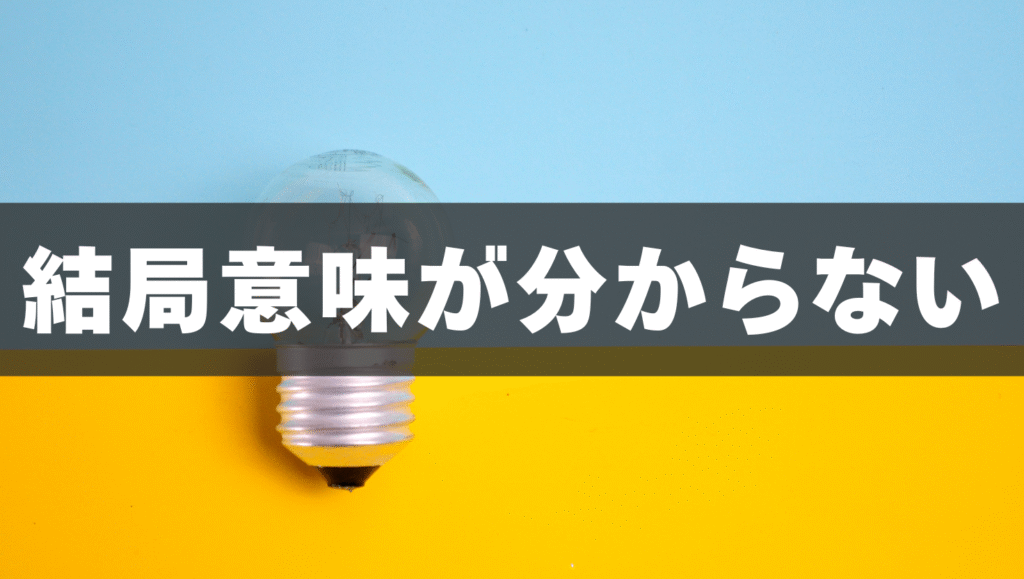
まずはリスニング編から解説していきます。
聞き流すだけで英語の発音に耳が慣れるというのであれば、まぁ確かに何度も聞いていれば発音の特徴くらいは掴めるかもしれません。
しかし皆様が聞き流す理由は特徴を捉えようとしているのではなく、「いつか聞き取れる(意味がわかる)ようになりたい」という最終目標の達成のためですよね?
だとしたら聞こえてくる音に耳を慣れさせたとしても、その英文の意味が分からないと皆様の目標達成には近づけません。
では想像してみてください。
明日から毎日アラビア語のラジオを流し続けたら、1年後にはアラビア語で挨拶や基本的な日常会話ができるようになりますか?
答えはもちろんNoでしょう。
ラジオや洋楽を聞き流す上で大切なのは、その音が何と言っているのか、意味を確認することです。
歌詞やスクリプトの文字やその意味をきちんと確認し、そこで初めて音声と一致させて「聞き取れた」となるわけです。
洋楽をまずは音楽として楽しく聞いて、歌いたくなるくらい好きになってからその曲の歌詞を調べて本格的な学習に入る、という方法でしたらリスニング学習の入り口としては有効ですよ!
②「聞いて分かる」と「話せる」は別

今度はスピーキング編について解説します。
かなり前にゴルフの石◯遼選手が◯ピードラーニングという聞き流す教材を使って英語が話せるようになった、みたいな広告をよく見かけましたが、ああいった教材も本来ペラペラになるための教材ではありません。
そもそも石◯遼選手があの教材以外に何の英語学習もせずに英会話を上達させたと思いますか?
もし彼の英語の基礎知識が元々高かったら?
彼には教材を聞く時間以外に沢山ネイティブスピーカーと試合会場で話す機会があったとしたら?
実は教材の出版元の会社からスポンサー報酬だけ受け取っていて、実際は少ししか教材を使ったことがないとしたら?
誰も実態は分からないのに、「この教材でこの人はこんなに伸びました!」という謳い文句に誘われて手を出してしまうんですよね。
確かに耳は英語に慣れて音は聞き取りやすくなるかもしれませんが、なぜそれを聞き続ければスピーキングまで伸びるのでしょうか?
音を聞き取る能力と英語を話せる能力は全く別です。
リスニングテスト満点の東大生がペラペラとは限らないのと同じ。
ネイティブスピーカーのように英語をスラスラ話せるようになりたければ、自分で実際に発話してどんどん英単語を使っていきましょう!
「受け身学習」から脱却しよう!
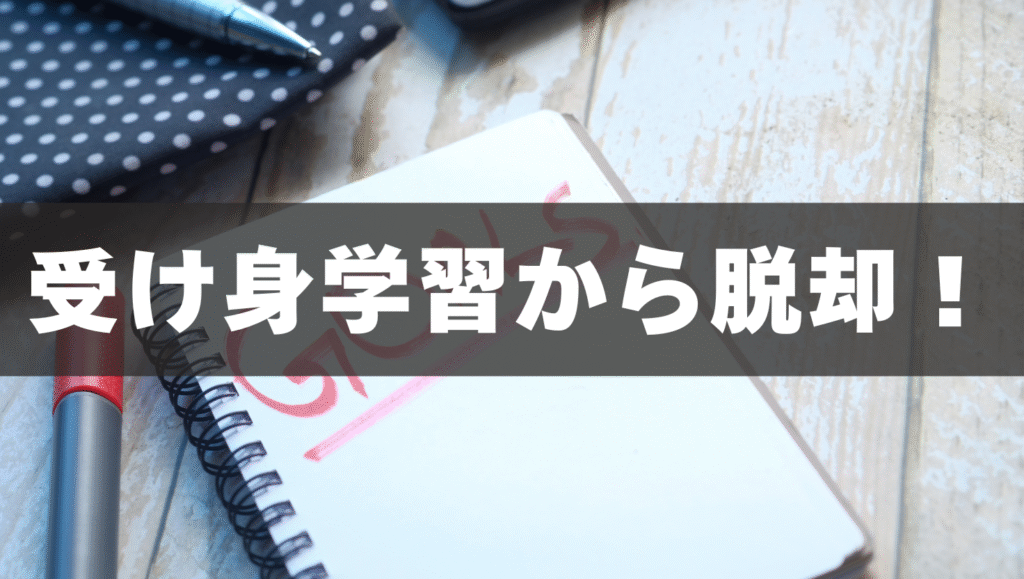
ボーっと生きているだけで勝手に耳から英語が入ってきて無敵になれる受け身の学習法など存在しないということが分かったところで、皆さんに一度考えていただきたいことがあります。
「今なんのために英語を勉強しているか?」です。
このゴール設定が曖昧であれば曖昧であるほど、楽な学習に逃げてしまいたい気持ちが強くなります。
英語を身につけた結果、将来どんな姿になりたいかという像がハッキリ決まっていればいるほど、どんな試練も乗り越えられることでしょう。
楽な学習に逃げて無意味な教材にお金を払ってしまう前に、今一度ご自身の心と向き合う時間をぜひ作ってあげてみてください♪