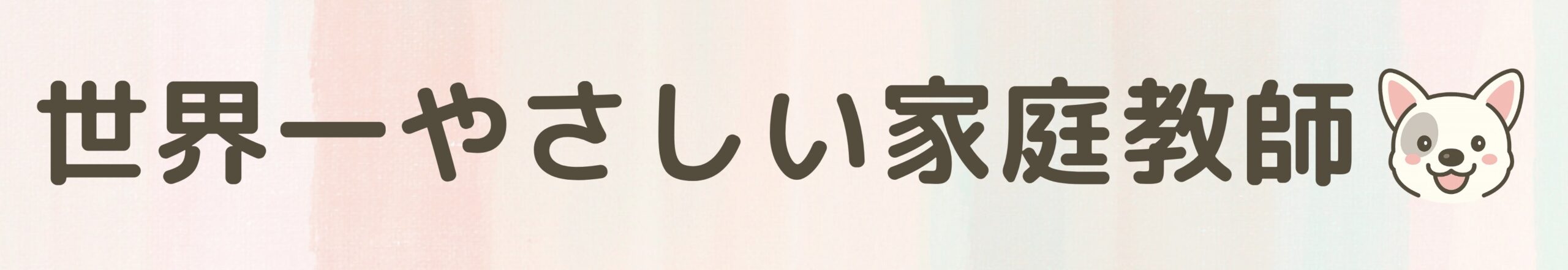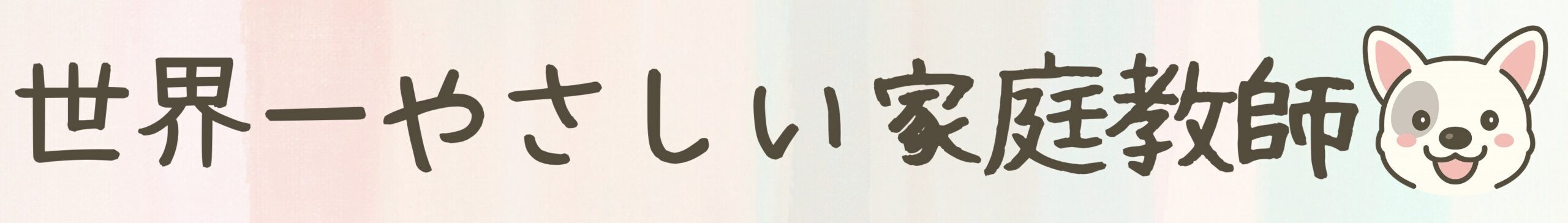こんにちは!
“世界一やさしい英語講師“として活動中のRikaです♪
普段は小中高生向けに超やさし〜い家庭教師をしたり、社会人向けに全然怒らない甘〜い英語コーチをしております♪
この記事では、学校の成績に伸び悩む中高生に本当に必要なものについてお話しさせていただければと思います。

成績が下がるとついつい学習量が足りないって思ってしまうよね。

もちろん勉強量を増やすことであっさり成績を上げられる場合もあります。
ただし多くのケースでは成績以前にもっと大切な土台が欠けていることが多いんです。

もっと大切な土台?それって勉強に関係あること?

はい!大いに関係ありますし、むしろそれが無ければ勉強が始まりません!
今回の記事が「うちの子は勉強量が足りないのでは?」などと頭を悩ませている中高生の保護者の方々に何かのヒントになれれば大変光栄です!
成績が伸びないのは「勉強量の問題」じゃない
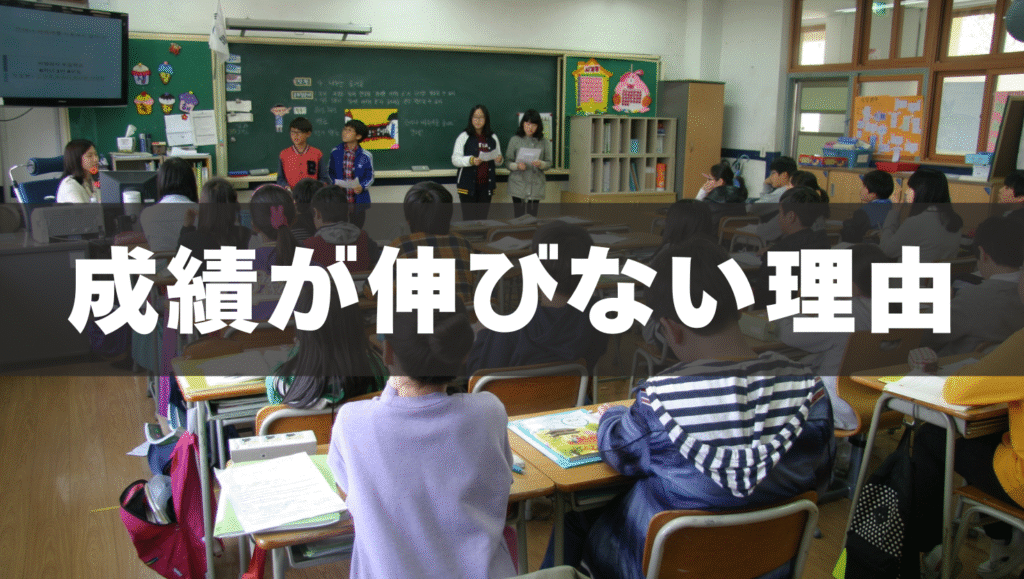
「うちの子は成績が悪いからもっと勉強させなきゃ!」
「夏休みの間は塾の夏期講習で沢山勉強させよう!」
お子さんの成績が思うように伸びないと、ついつい焦ってそのように考えてしまう保護者の方、実際多いのではないでしょうか。
確かに、学習時間はある程度は必要です。
毎日宿題はしなきゃいけないし、テスト期間はテストのための対策をする勉強時間が求められます。
でも、その子なりに一応頑張ってはいるのに、テストや成績の結果に努力が直結しない子がいるのもこれまた事実。
実はその原因に、その子の「心の状態」が関与していることがかなり多くのケースであるのです!
そしてまた、かなり多くの確率でその心の状態は見落とされがち、スルーされがちです…。
どれだけ机に座る時間を増やしても、塾の夏期講習に沢山お金をかけても、その子が「自信がないまま」、「不安を抱えたまま」では、本当の意味で努力を結果として発揮しにくいのです。
実は多い「自信がない子」の学習の悩み
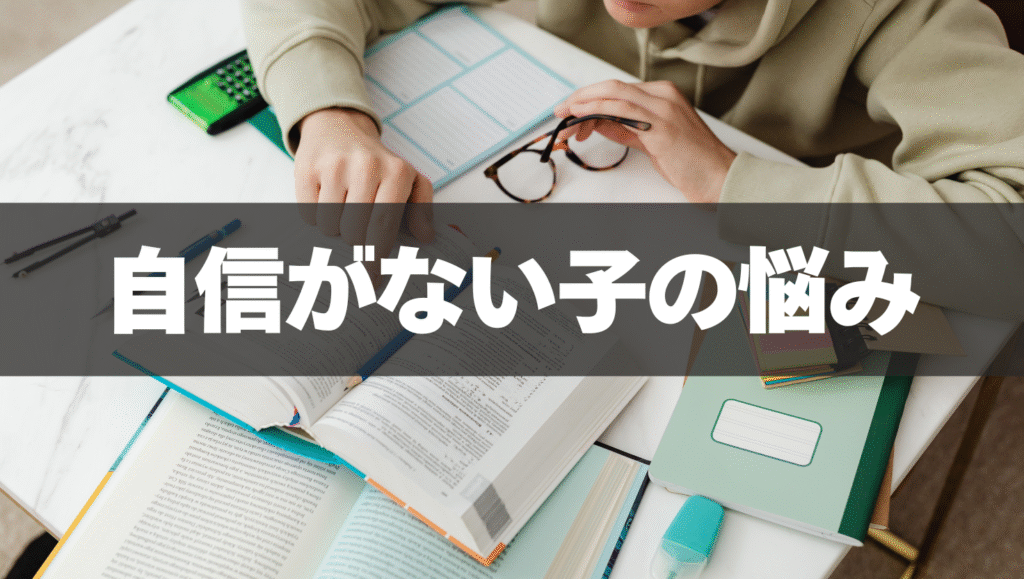
一見、「やる気がない」ように見えるお子さんでも、実は心の中ではやる気がないのではなく、
「やる気がまだ少しはあった頃に一度頑張ってみたが、結果に表れず拗ねてしまい今は諦めモード。」
「テストで良い点を取りたい気持ちはあるけど、仮に頑張っても結果に繋がらなかった時にガッカリしたくない。傷つくのが怖い。」
「テスト範囲は少し見てみたが、自分が一体どこでつまづいたのか、何が分からないのかということすら分からず、そっと教科書を閉じた。」
などと彼らなりに様々な葛藤をしていることがあります。
というか、ほぼ全員がそうです!
入学初日の1日目の授業からやる気のない学生なんていません。
みんな最初はやる気を持って授業を聞いて、どこかのふとしたタイミングでついていけなくなり、ある日のテストで「点数」という形でハッキリと周りより自分が劣っていることに落胆し、そこで初めて自信を失います。
この「自信のなさ」は、のちに授業を聞く意欲や集中力を奪いますし、
「どうせまた点数低いんだろうな…」
と、しまいには最初から努力する土俵にも上がろうとしない諦めモードを生んでしまい、永久に成績低下の負のスパイラルに陥るきっかけとなってしまうのです。
• 頑張っても成績に繋がらずに傷つくのが怖い
• 不明点を質問したり解決するのが億劫だから放置
• 劣等感から「どうせムリ」と決めつけて最初から勝負に出ない
• やる前から諦めた体裁を整え無意識に自分を守っている
こういった状態では、たとえ机に向かっても、せいぜい微々たる程度の点数アップしか期待できませんし、テストが終わったらまたその子は勉強から逃げてしまうでしょう。
このように、定期テストや受験前のその場しのぎの短期集中型の勉強量の増加では本当の意味で成績を伸ばしたり、教養を獲得するという真の学びにはなりません。
こういった理由から、私は自分の生徒たちには学習時間の増加ではなく、まず自信をつけてもらうことを強くオススメしています!
オススメというか、私が無理矢理彼らに自信つけさせてます!笑
自信をつけさせる方法4選
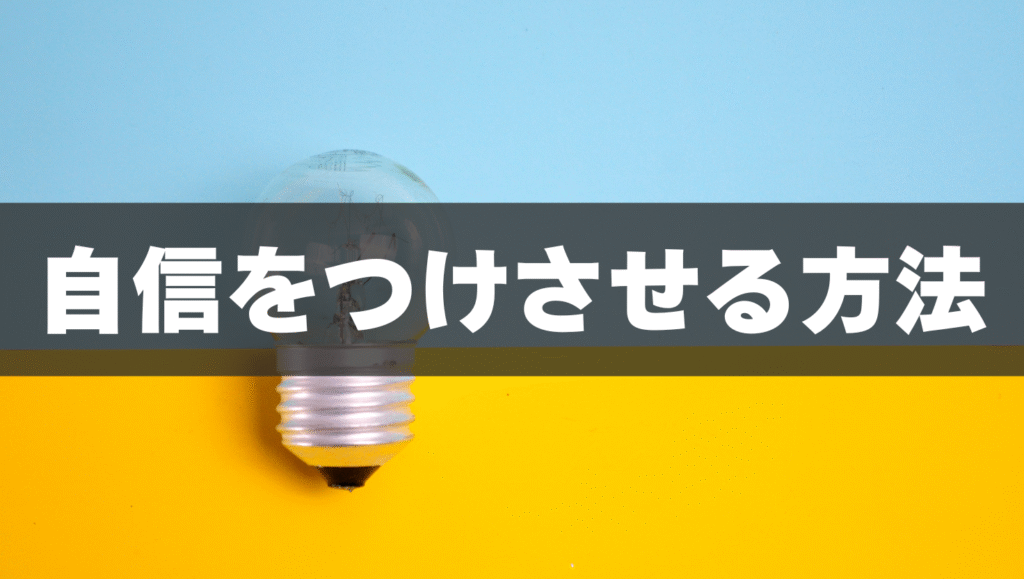
さて、成績アップに自信がいかに肝心な要素かある程度お分かりいただけたところで、今度は具体的な自信のつけさせ方についてご紹介したいと思います。
子供の自信を取り戻すための方法として、実にさまざまな種類のアプローチがありますが、ここではシンプルに4つの軸にまとめてご紹介いたしますね♪
4つとも実際に私が生徒たちに多用している方法なので、効果抜群だということは保証いたします!
① とにかく褒める
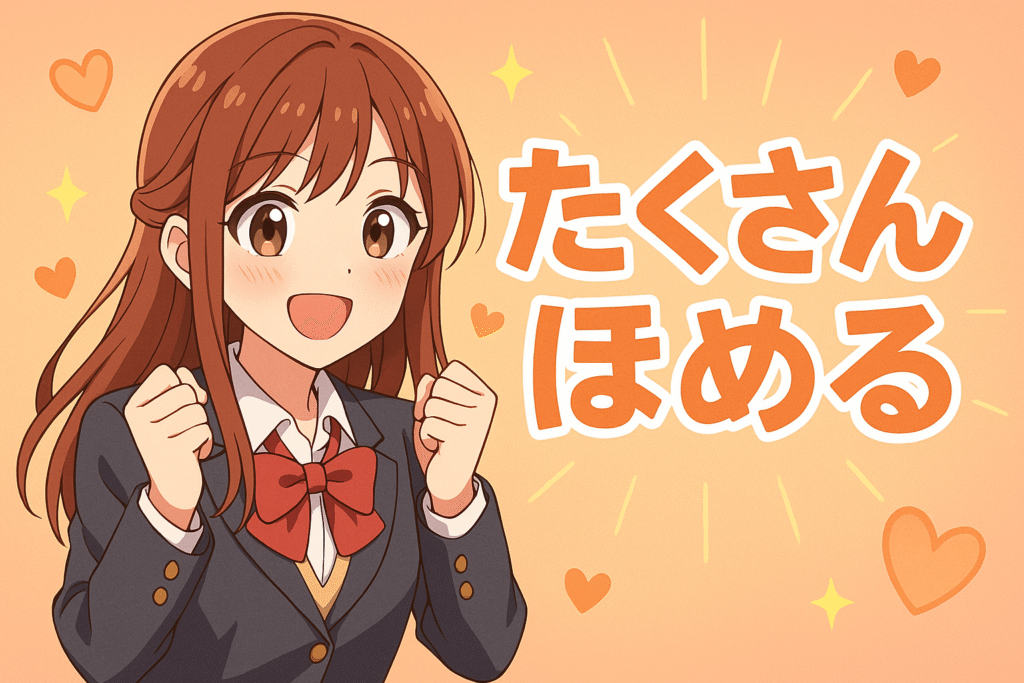
大人でも子供でも、褒められて嫌な思いをする人はなかなかいませんよね!
たいして自覚のないことであっても、ふと人から褒められると、
「ひょっとして自分、センスあるのかな?」
なんて思っちゃったり、不思議と急にやる気が湧いてくるものです。
日頃からこの褒める頻度をできるだけ増やせるよう、常に心がけています。
「ただ褒めるなんて子供騙しだ!」
と、思われるかもしれませんが、単純なように見えて、この褒めるという行為には絶大な自信を与えるパワーがあります!
宿題を終えたとか、アルファベットの字の書き方が綺麗だとか、テストが一点だけ上がったとか、どんな些細な成果でも構いませんので、まずはその子が「できたこと」、「がんばったこと」に対してしっかりとほめること!
答えが合っていなくても、
「考え方は良いよね!」だとか、
問題を解くのが遅くても、
「前よりだんだん速くなってきたね!」とか、
小さな進歩も見逃さずに「あなたはちゃんと成長しているよ」と伝えること。
その子の成果を認めてあげることで、たとえ一時的であっても「自分はできるかもしれない」という錯覚を生み、それは次の行動につながります!
自信が育つと、学びに向かう姿勢が格段に変わるのです!
まずはたっぷり認めてあげて、「よし、やってみよう」と前向きに挑戦できる気分にさせてあげましょう♪
② 否定しない
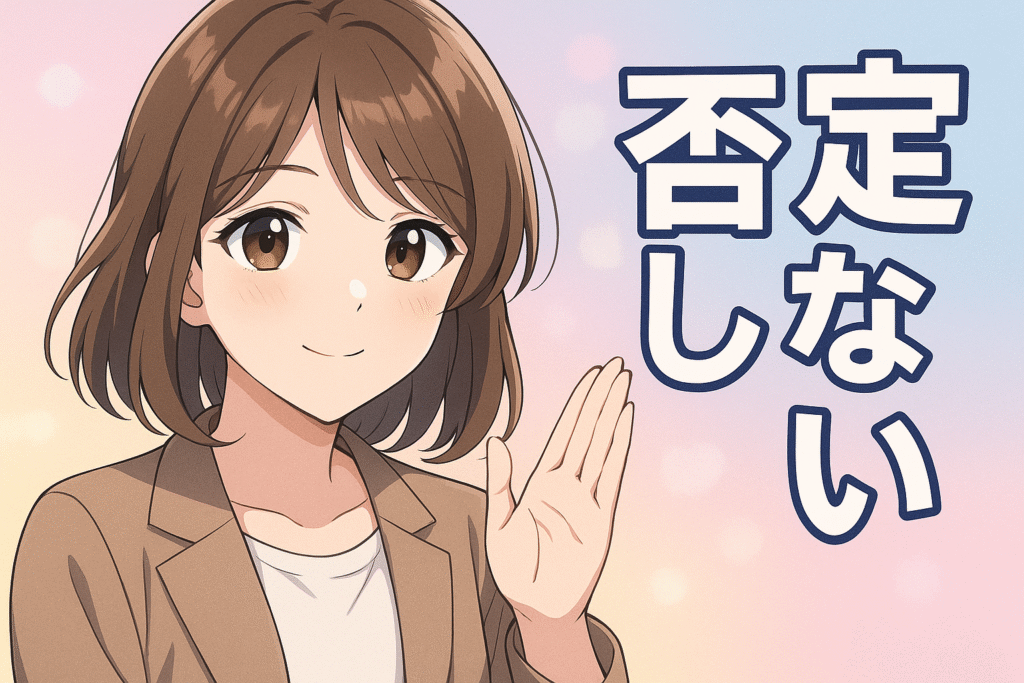
「なんでわからないの?」
と、悪気はなくても純粋につい聞いてしまう家庭教師、世の中たくさんいるんです。
否定的な言葉は苦手意識を深める原因になります。
ほかにも、問題を間違えた時に
「違うよ」
「間違ってるよ」
などという指摘する言葉も自然と使ってしまってる先生、多いはず。
その子が問題を間違えたとしても、「違う」という言葉をできれば使わないであげてほしいんです。
私なら、生徒が超的外れな回答をしたとしても、
「あ〜近いけど惜しいな!」
「なるほどね、発想は確かに納得した!」
「あ、ごめんね、たぶん私の説明が下手すぎたわ」
のように絶対ネガティブワードは使いません。
ネガティブなワードを向けていいのは子供に対してじゃなくて自分に対してだけですよ!
ほかにも、例えば生徒が間違えた回答にバツも書きません。
生徒が間違えて回答を書いても、あとで正しい答えに書き直したらその上から◯をつけちゃいます。
生徒の答案は◯でいっぱいに埋め尽くしたい!
赤ペン先生じゃないんだから、生徒が自分で間違いだとわかっていれば、教師がバツなんてわざわざつける必要ないです。
否定される回数は少ければ少ないほど良いし、なんなら0が良いです。
こんなふうに、「絶対に否定されない」、「全肯定してもらえる」環境でこそ、子どもは自由に発言し、「わからない」と素直に質問できるようになります。
褒めることと否定しないことは2つセットで最大の効果を発揮しますので合わせ技がオススメ!
絶対に否定されず安心して学べる空気感が、生徒の自信を支える土台になります。
③ 共感する

共感はその子が壁にぶち当たった時に特に有効なアプローチです。
例えば、お子さんが「難しい」、「やりたくない」と言ったとき、
「難しくない!」
「やろう!」
「でもやらなきゃ!」
と、ド正論で返さないように気をつけたいところです。
「だね〜これはさすがに長すぎて読む気失せちゃうかも」
「先生も昔これ大嫌いだったよ!」
「こんなの読めるだけでも相当レベル高いよね」
など、一旦は気持ちに寄り添ってみてください。
ほかにも、
生徒「今回はテストが難しかったから点数下がった」
→「なるほどね!じゃあ仕方ない!」
生徒「眠くて授業中寝ちゃってた」
→「だって最近部活ハードだもんね!」
生徒「勉強したところがテストに出なかった」
→「それは神のイタズラすぎるね!」
のように、少々大袈裟な言い方をする時もありますが、その子と同じ目線で気持ちに寄り添ってあげましょう!笑
「この人は自分と同じ価値観なんだ」
という安心感が生まれると、子どもは質問したり、意見を言ったりすることへの抵抗がなくなります。
回答を思いついたらあまり自信がなくても間違いを恐れず口に出せるようになりますし、進路や成績に対する正直な感想も共有してくれるようになります。
ただ聞いて欲しくて口に出していることに対して、大人が正論で論破する必要はありません。
本人は聞いて欲しくて言ってるだけなんだから、聞いてあげましょう。
④ 応援する

スポーツでも勉強でも仕事でも、応援の力は偉大です。
「誰かが応援してくれている」
「誰かが自分の成功を期待している」
と意識するだけで、不思議と頑張れることがあります。
自分1人しかいない世界なら孤独に頑張るだけですが、自分は期待されているんだと感じることで、「その応援に応えられるよう頑張ってみよう」と思えるのです。
「どうせまた点数低いんでしょ?」
「どうせ今回も全然勉強してないんでしょ?」
「またこの点数か。そろそろ慣れてきたよ」
などとネガティブな言葉をかけていませんか?
「挑戦したい気持ち」を後押しするのはポジティブなエールです!
優しくない言葉で子供の士気を下げないよう気をつけたいところです!
「子供の自信」を甘く見ないで!
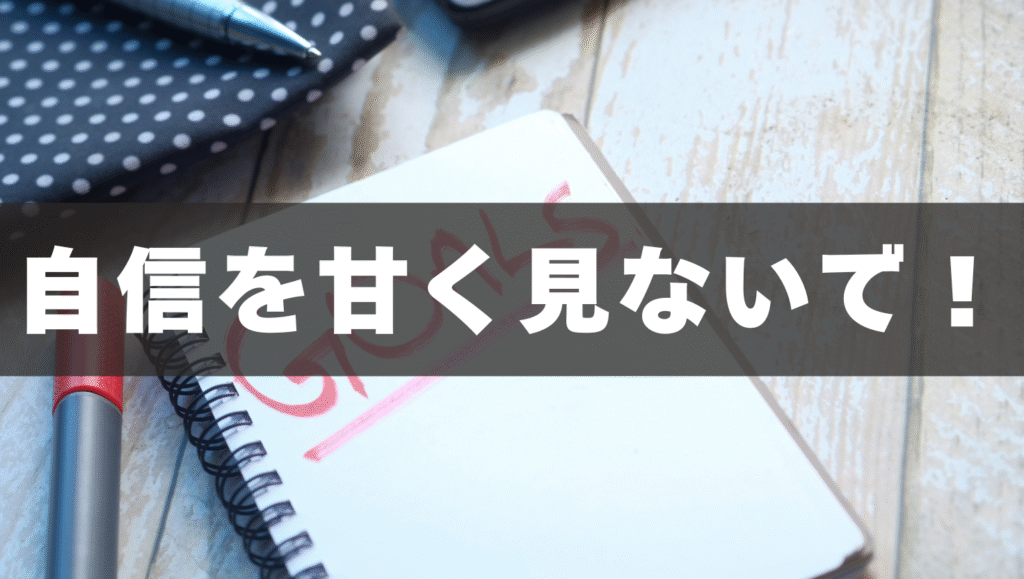
何度も繰り返しになりますが、勉強に向かうためには、まず「やってみよう」と思える気持ちが必要です。
そのやってみようという気持ちをつくることができるのは「自信」。
自信を持てるようになれば、
→自然と行動が変わる
→結果が少し出る
→自信が増す→(以降繰り返し)
の最強のループにハマることができます!
まずは、その子自身をたくさん褒めて、気持ちに寄り添い、信じてあげる、応援してあげること!
成績や学力そのものに向き合う前に、気持ちに寄り添う視点を持つことが何よりの学習支援になると私は信じています。
今回ご紹介した4つ全てのアプローチを明日から急に実行するのは少々難しいかもしれませんので、まずは否定的な発言をやめることだけに意識を向けてみてはいかがでしょうか?
皆さんのお子さんが良い心の状態で学習に向かってくれることを願います!!
最後までお読みいただきありがとうございました!💖