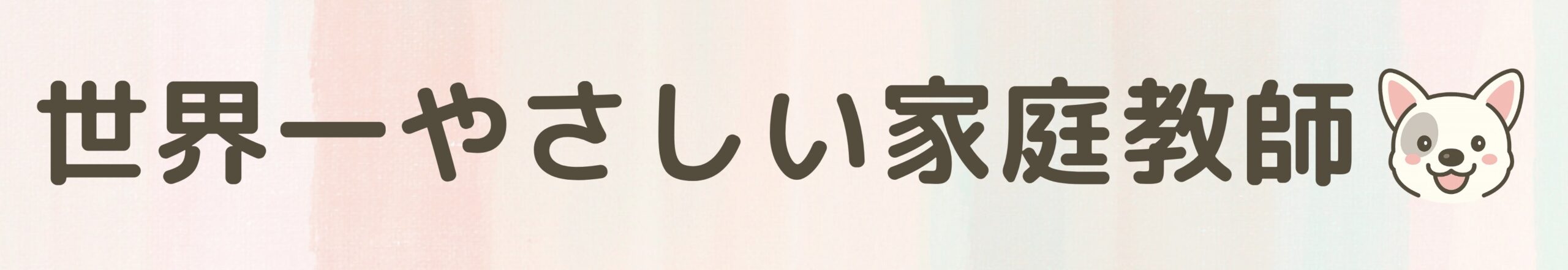こんにちは、”世界一やさしい英語講師“として活動中のRikaです♪
この記事では、親の愛情がかえって子供の成績低下の原因をつくってしまう非常に良くある事例を厳選して3パターンお伝え致します。

ご両親はきっと子供のために一生懸命なんだよ。それが上手くお子さんに伝わると良いのにね。

そうですね。もちろん愛情はたっぷり伝わっていると思いますよ。ただ、親の言うことが正しいか正しくないかに関わらず、彼らなりに耳が痛いと思ってしまう瞬間もあるようです。

たしかに勉強しなさいって言われれば言われるほど、不思議と逆にやりたくなくなってしまう気持ちは少しだけ共感できるな~。

人間の心理ですね。子供のやる気をこれ以上削がないためにも、今回の記事が保護者の方々に少しでも参考になれば幸いです。
分かり合えない親子
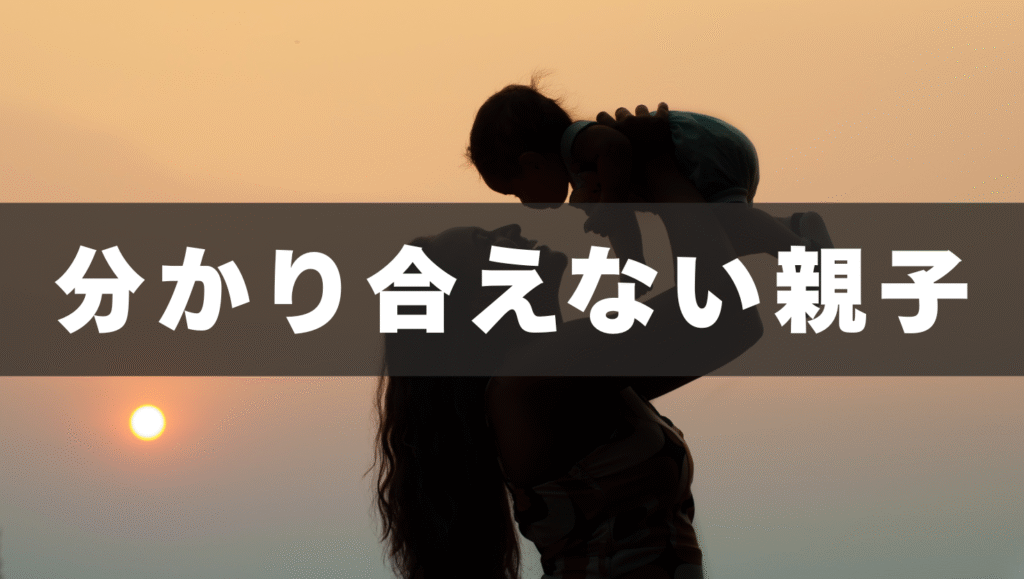
これまで家庭教師としてたくさんの中高生と会話をしてきました。
その中で気づいたことは、保護者の方が思っていることと、お子様が思っていることに、相当大きなギャップがあるというものです。
通常、事前に保護者の方からヒアリングした情報をもとにして、お子様と無料体験授業・カウンセリングを行うのですが、その時のお子様の発言や様子があまりにも事前のヒアリング内容と違いすぎてビックリした経験が何度もあります。
「親の心、子知らず…トホホ…」
と、親は思っているのでしょうが、同じように子供も、
「子供の心、親知らず…」
と思っているのです。
せっかく子供のためを思ってあれこれ考えている保護者の方の深い愛情が、できればそのまままっすぐにお子様に伝わってほしいと思い、今回の記事の執筆に至りました。
子供の成績低下の原因3選
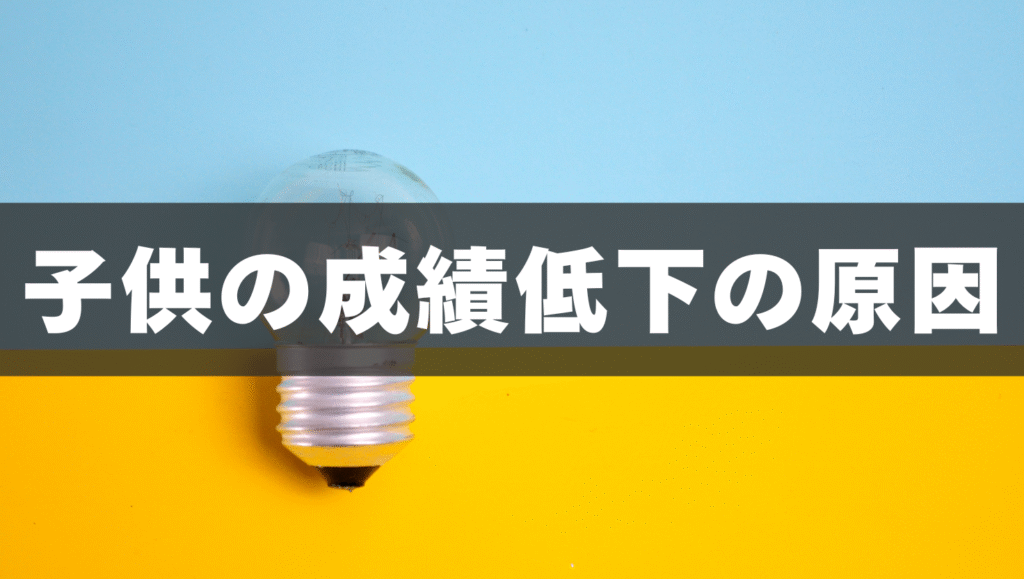
子供に限らず、人は誰しも面倒なことが嫌いで、楽な方に逃げるのが大好きな生き物です。
勉強が嫌いになったり成績が下がる原因が、決して全て保護者のせいだとはもちろん思いません。
しかし、親が知らず知らずのうちに原因になってしまっているケースは本当によくあることですので、その中でも典型的なあるあるパターンを今回は以下3選お伝えしたいと思います。
①勝手に「苦手」と決めつけている

意外に多いのがこの決めつけパターンです。
「うちの子は英語が本当にダメで…」
「英語が得意になってくれれば将来役に立つのに…」
という事前情報を鵜呑みにして、いざお子様と初回カウンセリングすると、
「英語そんなに苦手じゃないよ?」
「むしろクラスではまぁまぁできる方だよ?」
という意外な反応がお子様から返ってくることがあります。
親が「うちの子は英語が苦手に違いない!」と思った根拠は、下がり続けるテストの点数や、英検に落ちてしまった事実など、もちろん色々あるのでしょう。
では、もしクラスの平均点も同様に下降傾向だったら?
もしお子様の所属する学校が全国平均より高いレベルの教育をしている難関校だったら?
もしお子様のクラスの英語教師が作るテストが、のちの受験対策を見越して意図的に複雑すぎる内容に作られていたら?
もし万全な対策をして英検に臨んでいればあっさり受かる程度のポテンシャルをお子様が既に持っているとしたら?
この手のお子様に「お前は英語が苦手だ!」と勝手に決めつけてしまうと、実は本当は苦手ではなかったのに徐々に苦手意識が生まれてしまい、
本人は苦手と思っていない→本人が苦手と自覚
のようなもったいない状況を生んでしまいます。
勉強の遅れは塾や家庭教師で簡単に取り戻せても、失った自信はそう簡単には戻ってきません。
子供の心は大人よりも脆くて繊細ですからね。
「うちの子、英語苦手かも…」
と思ったとしても、勝手に苦手だと決めつけて本人の苦手意識を呼び起こさせないように注意したいところですね!
②本人より親の方が必死

1番多いケースがこのパターンです。
中学受験とか多分こんな感じですよね。
本人よりも親が相当ジタバタ焦っており、当事者である子供は、
「この人たち、成績ごときで一体何をそんなに騒いでいるのだろう?」
くらいにしか思っていないケース…(笑)
子供が自分で事態を飲み込んで諸々自覚するよりも前に、あまりにも親が騒ぎ立てるので、冷めちゃうというか、自分のことなのにますます客観的に見えてしまうんでしょうね…。
親心としては、愛する我が子の将来を案じて助けてあげているつもりなのですが、やりすぎると本人が当事者意識を持つ機会を奪ってしまいかねません。
もっとひどい場合は、その子の志望校が保護者の望む志望校になってしまっていることさえあります。
志望校は自分で行きたいと願って決めるから合格に向かって頑張れるものです。
成績低下も受験も、自分ごと化させるために、あまり手を出しすぎないことも必要です。
アドバイスと介入は似て非なるものです。
あれこれ言いたくなる気持ちをたまにはグッと堪えていただき、見守る姿勢も持ちましょう。
案外放置された方がかえって子供は自発的に行動することもあるんですよ!
③強制しすぎて学ぶ楽しさや意義を失う
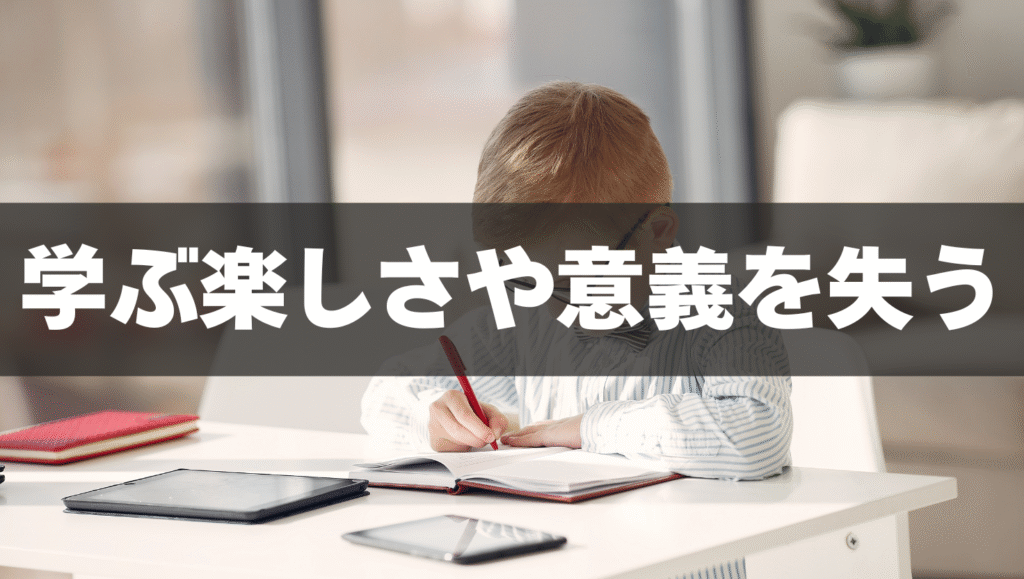
勉強は本来自分で必要と考え、自分のために努力するもの。
あるいは、分かって楽しい、学ぶ過程が楽しいと思いながら興味の赴くままにするものです。
どちらにしても自ら進んで自発的に取り組むことが重要と考えます。
「周りが言うからなんとなく指示されるがまま勉強してきました」
といういわゆる脳死状態で作業のようにこなす勉強の先に、親が期待するような幸せな子供の未来は待っていますでしょうか?
そんな風に育った子は、仮に将来立派な会社に入社できたとしても、同じように脳死で上司に言われたことだけを淡々とこなす作業人間になってしまうかもしれません。
「やりなさい!」というような強制させる発言は極力控え、勉強をすることの意義や、その先に何があるのかといった会話をするというのはいかがでしょう?
会話でしたら一方通行ではなく、子供の声にも耳を傾けることができますからね。
我が子が何を考えているのか知れる良い機会にもなりますよ。
学生は小さな大人

彼らは幼児のように手を引っ張ってあげないと歩かないわけではありません。
大人に比べたらまだまだ未熟な点があったり、うまく思考もまとまっていないかもしれませんが、彼らには彼らなりの理論・こだわりを持っており、それを正しいと思って進んでいます。
それらを真っ向からただ否定するのではなく、彼らを小さな大人として捉え、たまには対等な目線で会話をしてあげると、あっさりと素直になってくれたりもします。
ぜひ「叱る」→「対話」に移行してみてはいかがでしょうか?