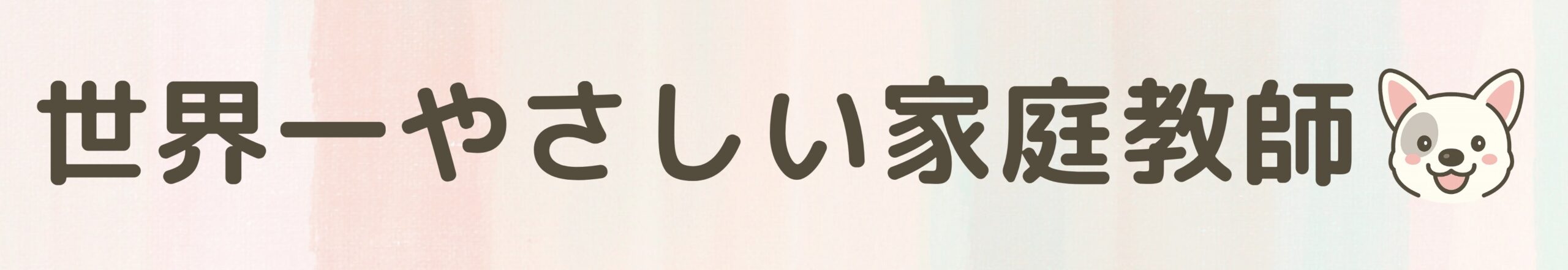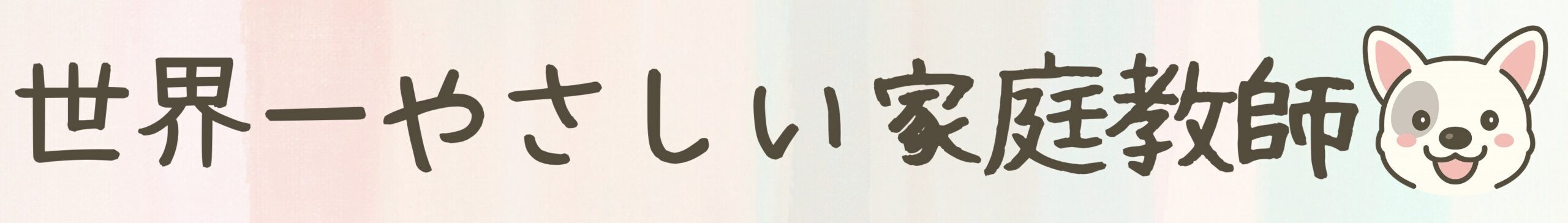こんにちは!
“世界一やさしい英語講師“として活動中のRikaです♪
普段は小中高生向けに超やさし〜い家庭教師をしたり、社会人向けに全然怒らない甘〜い英語コーチをしております♪
この記事では、スパルタ式の学習法が合わないタイプのお子さまの学習環境で気をつけたいことと、今日からご家庭で実践していただける成績UPにつながる効果的な学び方の工夫について解説します📚✨

スパルタ教育か~。確かに合わないお子さんはたくさんいるかもね。

そうですね、もしかするとスパルタ式で成績が振るわないお子さんは、「頑張っていない」のではなく「頑張り方が合っていない」可能性があります🤔

じゃあそういう子は今日からどうやって学べばいいのか教えてよ!

はい、もちろんです♪
「うちの子はこのままで大丈夫なのか…😭🌀」などと、お子さんの成績に不安を抱えている保護者の方々にもこの記事が何かのヒントになれれば幸いです!✨
やる気が出ないのはつらいから?🤔

あなたのお子さまの勉強に対する姿勢は、以下のような傾向にいくつか当てはまりますでしょうか?👀
「机に向かってもすぐに集中が切れる✏️」
「せっかく塾に入ったのに成績が伸びない🌀」
「ちょっと注意しただけで拗ねる🙁」
「課題/宿題を出しても手をつけない📖」
「勉強に関して何か尋ねても答えようとしない🤐」
毎日そんな姿ばかり見ていると徐々に心配になってきますよね😅
「うちの子は勉強に対してやる気がないのでは?🤔💦」
と疑ってしまうこともしばしば…😥
でも本当は、
「やる気はあるけど自信がないだけ」
「何から手をつけていいか分かっていないだけ」
「頑張っているのに認めてもらえず悲しいだけ」
「どうせ否定されるから何も答えたくないだけ」
など、心の中は「怠惰」ではなく「つらさ」や「不安」がたくさん隠れていることも多いのです😢💦
特に、真面目、繊細、感受性の強いタイプのお子さまほど、こういった悩みを抱えている傾向にあります💔
そして、彼らは誰よりも自由な環境を好み、そこで本来の力を発揮します🗽
だからこそ、こういったお子さまには一緒に自分に合ったペースでゆっくり考えてあげられるサポートが本来必要なのですが、我が子を想うあまり勉強を強制したり、あれこれ詰め込んでしまう親心もとってもよく分かります😓✏️
スパルタ式が合わない4つの理由🌀

スパルタ式の教育にも利点はたくさんありますし、相性が良いお子さんなら飛躍的に伸びる可能性も十分にあります!👍⭕️
ですので詰め込み型の教育は決して間違いというわけではありませんが、繊細で外部からの刺激に打たれ弱いお子さまにはこの手の教育ではなかなか効果を発揮するのが難しいというのも否めません💦
理由を順番に解説していきますね😀🎵
① 宿題の量で押しつぶされる
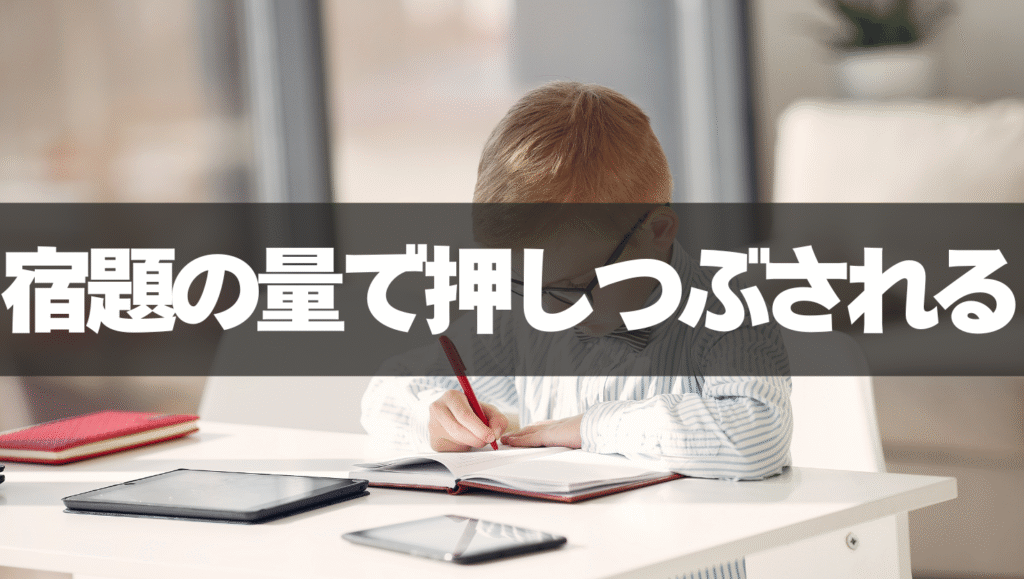
進学校やハイレベルな塾ほど、出される宿題の量が多いです📚📚📚
宿題を通して学んだことへの理解を深められるため、生徒のアウトプットの場として、出す側は良かれと思ってジャンジャン課してきます📚📚📚
もちろん解くためにはそれなりの学習時間を毎日確保しなければならないので、それが結果として勉強の習慣化に繋がる良い側面もあるのですが、
生徒「多すぎて提出期限に間に合わない!😭」
と、期限に対して真面目なあまり、締め切りには間に合って提出できているが、答えは解答を丸写しして出しているので、実質その子のためになっていないというケースも🌀
(※この解答丸写しケース、学校でも塾でも実はかなり多いので、皆さんのお子さまにも当てはまっていないか要注意です⚠️)
また、
生徒「こんな多い量を自分にできるはずがない!😭」
と、見ただけで戦意を喪失してやる気をなくしてしまう子も少なくありません💦
効果的なのは、その子にとって「やりきれる量」、「1人でもサクサク解ける程度の難易度」の宿題を選んであげることです☝️
「自分にも1人でできた!✨」
という小さな達成感と成功体験が、次の学習への意欲につながります😊💪
② 進度に置いていかれる

授業のペースが早すぎると、理解が追いつかないままどんどんカリキュラムの単元だけは進んでしまいます🏫💦
分からない内容にぶち当たってしまった時は即座に解決しないと、疑問が残ったまま次から次へと授業は進み、気づいた頃には取り残されているという事態に…😭
こういう場合は、あとでわからない部分をゆっくり確認できるように、一度立ち止まれる環境があると軌道修正がしやすいです👍✨
実際に、平日は塾に通いながら、週末は家庭教師の先生と塾の内容のフォローアップをしているというご家庭もたくさんあります🏠✏️
塾で新しい知識を素早くインプットし、家庭教師の先生とはゆっくり深掘りしながら不明点がなくなるまで内容をアウトプットしながら確認、という作業です📖
「自分は内容をきちんと理解できている!」という状況が学習に対する自信を生みます💪✨
③ 順位に心が折れる

集団塾や進学校だと、成績やテストの点数で校内順位をつけられたり、レベルに応じて教科ごとにクラス分けされたりと、常に周りと比較される環境に身を置かなければなりません😥
せっかく得意な教科だったとしても、順位やクラス分けが自分の思った通りの結果にならないと、かえって自信や意欲を奪う原因になってしまいます💦
ここで順位や成績を上げるために逆境をバネにできるタイプの子も勿論いるのですが、繊細な子は心がポッキリ折れてしまいやすいです💔
周りとの比較ではなく、昨日までの自分の理解度から今日はどのくらい伸びたか、という自分だけに集中・注目してあげる機会を設けてあげるとやる気を持ち直せますよ💪🔥
結果が出ずに劣等感を感じるとやる気までなくなってくるというのは大人でもそうですし、なにも特殊な現象ではありませんからね☺️
④ 高すぎる目標がプレッシャーに
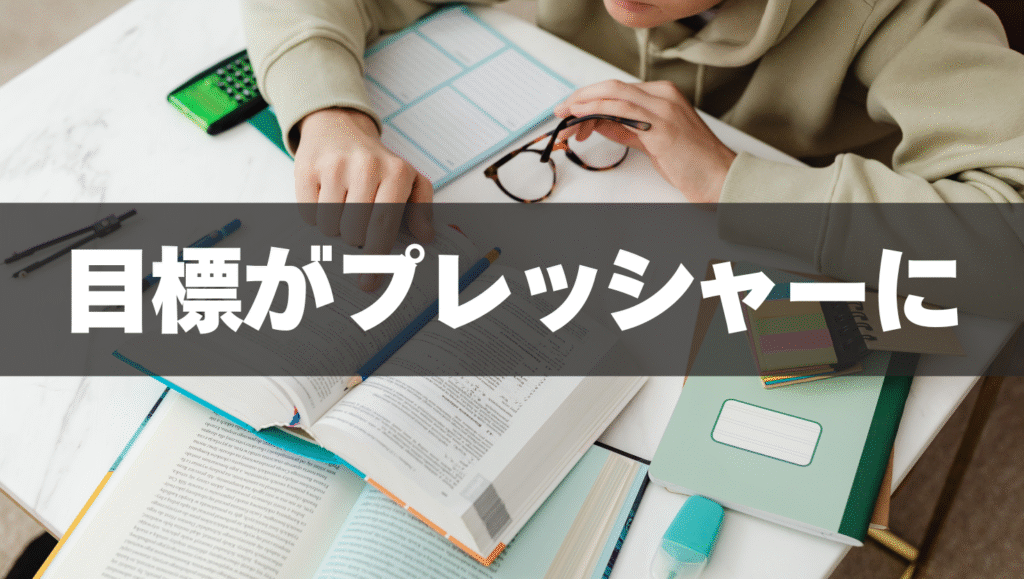
私の過去の記事で、何事も成功させようと思ったら目標が必ず必要ということを以前お伝えしました。
目標があることはとても大事なのですが、
「偏差値◯◯を目指せ!🥇」
「絶対◯◯大学合格!🏫」
「毎回全教科1位!🏆」
という目標がもし今の自分のレベルとかなり差があるようでしたら、それもまた逆効果なのです🌀
過去の記事でも詳しく解説しましたが、あくまで本人が本気で頑張りたいと思える動機が十分にあり、努力すれば達成できそうな現実味のある具体的な目標に設定しましょう💯
宿題の量の例と同じく、あまにり高すぎるノルマや目標はその子のやる気を削ぎます😥
ステージに合わせて都度目標は微修正が必要です💡
自分のペースで学びたい!

スパルタ式の学習法が合わないパターンをいくつかご紹介しましたが、どれもやる気や自信を失くしてしまうという共通点がありましたよね👀💡
そういった場合に、彼らが学習意欲のない不真面目な劣等生なのだという理解は間違っています☝️
真面目で繊細なお子さまほど、少しのハードルでさえも大きな障壁に感じてしまったり、ほんのちょっとした出来事がきっかけで自信をなくしてしまうのです💔
せっかくセンスや可能性があるのに、環境に順応できなかったことが原因で伸びなくなってしまうのはとっても惜しいと思うんです😢
子どもは不安感の強い環境だと、危険に対処する反射行動で、「考える力」よりも「逃げる反応」が優先されてしまいます🧠
安心感のある環境でこそ、その子の本来の力が発揮でき、そこで得られた小さな成功体験が「やる気スイッチ」になるはずです😊👍
家庭でできる学び方の工夫3選🏠
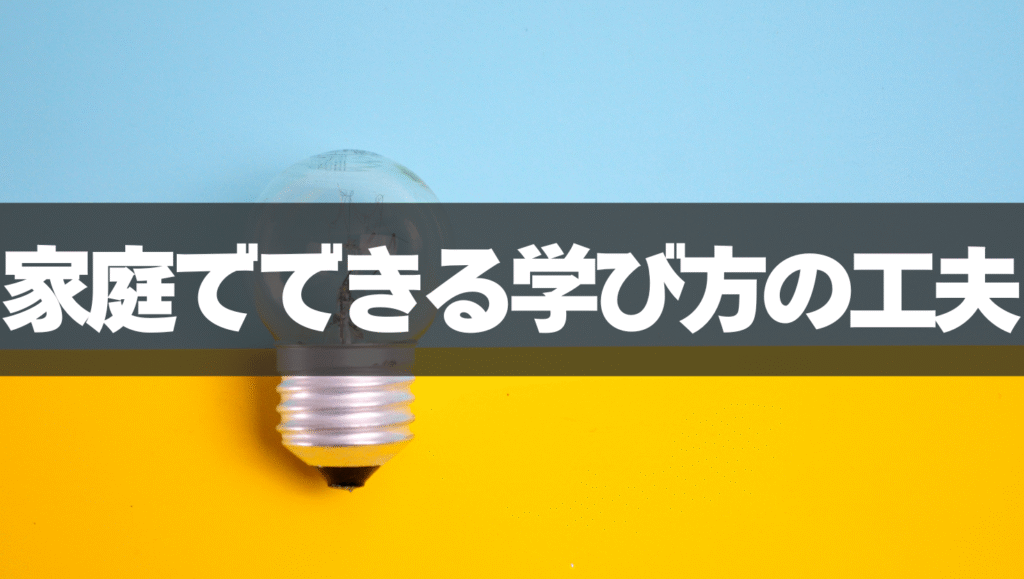
では、そういったお子さまに対してどんな工夫をしてあげられるでしょうか?👀🌱
今日からご家庭で始められる比較的簡単なアプローチを以下に3つにまとめましたので、ご自身のご家庭で実践できそうなものがないか、ぜひご検討いただければと思います😊🎵
①宿題は量より質📚
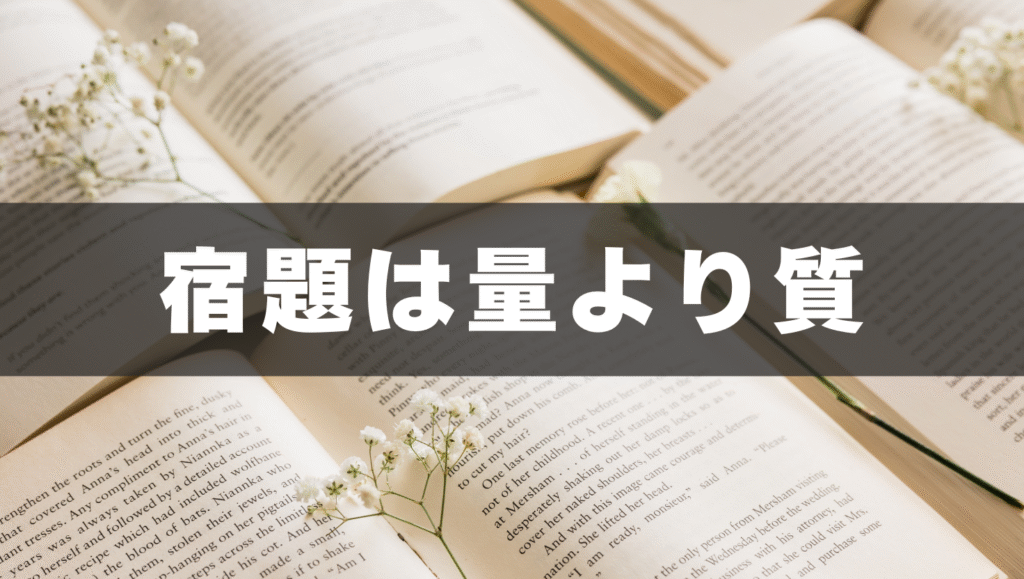
子ども「これ全部終わらせなきゃ💦」
という使命感が強くなると、学習意欲や好奇心が失せてしまうことがあります📚
たとえば、問題集を1冊をドーンと渡すよりも、
保護者「今日はこの1ページだけやってみたら?📖」
と量を絞ることで、
子ども「そのくらいならまぁやってもいいかな」
と前向きな気持ちになりやすいです😊
極端に勉強嫌いのお子さんの場合は1ページでなくとも、3問だけ、とかでも大丈夫ですよ👍✨
オリエンタルラジオの中田敦彦さんが、実際に学生時代に実践していた効果的な勉強法として、
「分厚い問題集を1冊買わずに薄い問題集をたくさん買って、1冊ごとに解き終わったら捨てる!📖捨てると達成感と解放感がある!✨」
とおっしゃっていましたが、この学習法では、
①学習に対するハードルを下げる
②もし1冊できた場合の達成感を目標にモチベーションを保つ
③実際に1冊完了した時の小さな成功体験を複数冊(何度も)積み上げる
という3つの有効な効果がギッシリ詰まっています!👏✨✨
こんな風に、一気にたくさん詰め込むのではなく、中身の詰まった質の良い問題に絞って少しずつ取り組ませると学習意欲を落とすことなく取り組みやすいですよね😊👍
ポイントは、子どもが無理しなくてもできそうだと思える量に調整すること🌟
子ども「やってみたら意外と全部できた!🎉」
という成功体験が次のやる気を引き出してくれますよ😊💪
間違いを叱らず、むしろ歓迎する👏

間違いは1番の成長のチャンス!✨
正解した時も勿論褒めてあげるべきですが、間違えた時に責めたり叱るのはNGです❌
「でも考え方は合ってたね!」
「発想は近かったね!」
など、結果だけでなくしっかりと過程にもフォーカスして、頑張りを認めてあげましょう👏
「ここが苦手だって気づけてよかったね!」
「知る良い機会になったね!」
と、失敗をポジティブに歓迎してあげると、
子ども「また間違えたらどうしよう…😢」
という不安感も減りますし、次回から子ども自身も素直に間違いを認めやすくなります😊
間違いは悪いことではないという刷り込みを家庭内で早速実践してみましょう🎵
他者ではなく過去の自分との比較
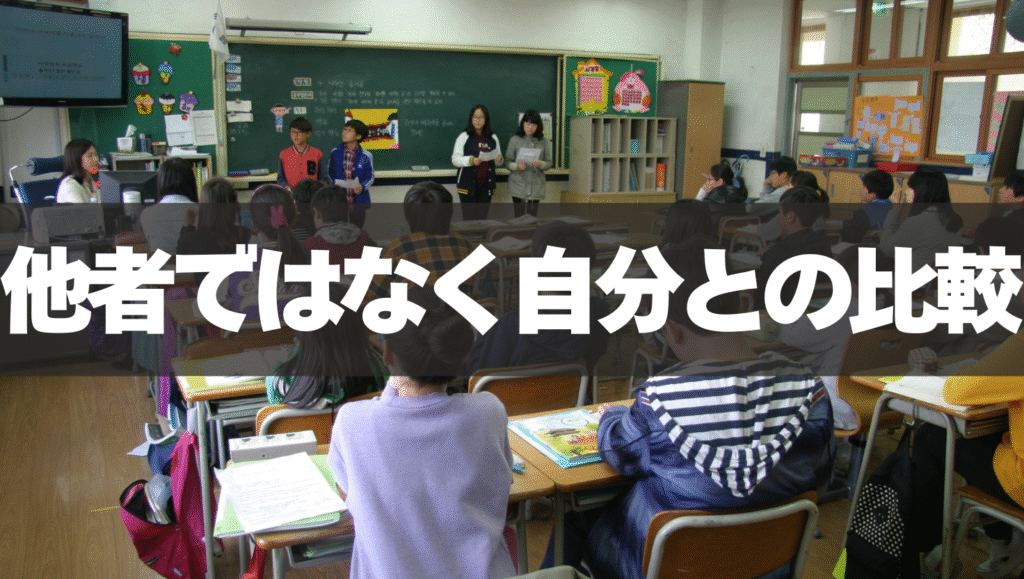
子どもは普段気にしていないように見えて、実は心の中では意外と周りと自分を比べて落ち込んでいたりするものです🥲
特に親の前では強がったり本心を言わない子も多いので、
「別に気にしてないよ!」
という体裁を整えておいて、本当は心が折れてしまっているパターンもあります💔
(私の生徒達も、実際に保護者さんの前での体裁と本人の本音が全然違うケース、たくさんあります!⚠️)
「同じクラスの〇〇くんはできるのに…」
「なんで自分だけわからないんだろう…」
そんなふうに思っていると、自信もやる気もどんどんなくなってしまいます💦
ここで大切なアプローチは、周りの誰かとではなく過去の自分との小さな変化に目を向けることです👀
たとえば、
「昨日は途中で諦めてたけど、今日は最後まで頑張れたね👏」
「計算ミスの頻度が最近減ってきたね👏」
「昨日より問題解き終わるの早かったね👏」
など、その子の過去と比較して成長したポイントを具体的に見つけてあげることで、子どもにとっては少しだけ達成感を得た気分になります☺️✨
「自分はちゃんと成長しているんだ!💡」
という実感があると、子どもはまた一歩自信を持って前に進んでいけます😊
その子に合う学び方がきっとある!

成績で苦戦している様子や、全然勉強していない様子、やる気がなさそうな様子を見ていると、保護者の方は不安になりますよね😥
でも決して「頑張れない」のではなく、「頑張り方が合っていないだけ」ということは本当によくあります💡
学びやすい形は1人1人違っていて当たり前です🌟
✔︎ 少しずつの達成感を大切にする🌱
✔︎ できたことを認める👏
✔︎ 無理に比べない❌
そんな学び方が、自分のペースを大切にしているお子さんを良い方向に導くエネルギーになります💪
お子さんが少しでも前向きに学習できるようにするためにも、本記事でお伝えした3つのアプローチのうちどれかお1つだけでもご家庭で早速実践していただけると嬉しいです😊💕
最後まで読んでいただきありがとうございました🥰